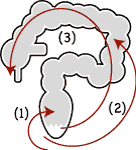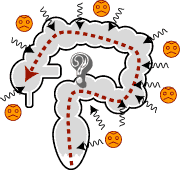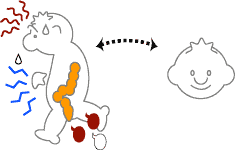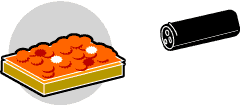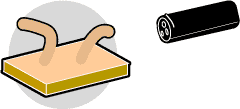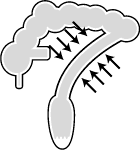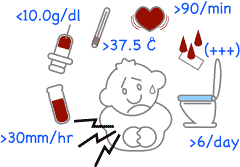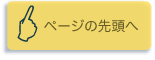大腸炎3 潰瘍性大腸炎の診断
潰瘍性大腸炎(かいようせいだいちょうえん)は病因不明の大腸のびまん性炎症性疾患で厚生労働省特定疾患です。粘膜から粘膜下層までの大腸の表層を主とした炎症で、肛門部より口に向かって拡がるのが特徴です。
いったんよくなっても(寛解=かんかい)、また病気がぶり返す(再燃=さいねん)ことも多く、気長に病気とつきあう必要があります。
病変の罹患範囲で(1)直腸炎型(2)左側大腸炎型(3)全大腸炎型と分類します(図1![]() )。範囲の広いものほど、難治性で長期間にわたり再燃を繰り返す傾向があります。
)。範囲の広いものほど、難治性で長期間にわたり再燃を繰り返す傾向があります。
発症のピークはは20代ですが、男女を問わず、若年者から高齢者まで発症します(図2![]() )。昔は日本では少ない病気でしたが、食生活の欧米化にともない急増しています。平成14年で77000人が特定疾患医療受給者証交付をうけ、毎年5000人のペースで増えています。
)。昔は日本では少ない病気でしたが、食生活の欧米化にともない急増しています。平成14年で77000人が特定疾患医療受給者証交付をうけ、毎年5000人のペースで増えています。
原因
自分の白血球が自分の大腸粘膜を攻撃する自己免疫疾患、と考えられていますが、遺伝の要因や、細菌やストレスの関与も考えられます(図3![]() )。
)。
症状
最初は下腹部を中心におなかがしぶり、下痢をして便に血が混じるようになります。症状が重くなると便に粘液、膿も混じり、発熱や腹痛もあらわれ、これがつづくと体重減少、栄養不良、貧血などがあらわれます。
大腸以外では、関節炎、皮膚病変(結節性紅斑や壊疽性膿皮症)、眼病変(結膜炎、虹彩毛様体炎)、心筋退行変性などがあらわれます。
このような症状が続いている時期を活動期、収まっている時期を寛解期とよびます。活動期、寛解期が繰り返しおきます(図4![]() )。
)。
診断
繰り返す治りにくい下痢で、発熱や粘血便をともなうとき、この病気を疑い大腸内視鏡検査をします。内視鏡で特徴的な所見があり、なお組織検査で確定診断となります。
注腸検査(大腸のバリウム検査)は昔はよく行われていましたが、大腸内視鏡検査がどこでも受けられるようになってからは、日本ではあまりされません。
内視鏡所見
初期には粘膜全体が腫れぼったくザラザラになり、粘膜の下の血管が見えにくくなります。内視鏡で少し触れただけで出血しやすくなり、粘膜表面にウミがついています(図5![]() )。
)。
さらに炎症が強くなると、粘膜表面がそげ落ち、びらんや潰瘍を多数作ります。通常は粘膜下組織までですが、重症になると筋層まで潰瘍が掘れます(図6![]() )。
)。
慢性化し、たびたび再燃をくりかえすと、緩解期に内視鏡検査をすると炎症性ポリープなどが観察されます (図7![]() )。粘膜は炎症のない時は萎縮して白っぽく、ひきつれが見えます。
)。粘膜は炎症のない時は萎縮して白っぽく、ひきつれが見えます。
さらに炎症が進むと、腸粘膜の萎縮や大腸の短縮とともに大腸の大きな襞(ハウストラ)が消失します。この変化は注腸検査で明らかです。ちょうど下水道管のようになる(lead pipe phenomenon)わけです(図8![]() )。
)。
全大腸炎型で、10年以上の長期にわたり再燃、寛解をくりかえしている人には、炎症を下地として腸上皮に異型細胞が現れることがあります。ときに悪性化して、大腸炎由来大腸癌(colitic cancer)ができますので、このような方は毎年大腸内視鏡を受けるべきです。
重症度分類
厚生労働省の重症度分類基準がよく用いられます。排便の回数、下血の程度、発熱、脈の数、血液検査での貧血の有無と血沈、これら6種類を組み合わせて、重症、中等症、軽症に区分します(図9![]() )。古典的ですが、簡単な臨床症状とどのような医療機関でもできる簡単な検査で分類できるのが長所です。重症度分類をくわしく知りたい方は、潰瘍性大腸炎の診断 補足の頁を参考に。
)。古典的ですが、簡単な臨床症状とどのような医療機関でもできる簡単な検査で分類できるのが長所です。重症度分類をくわしく知りたい方は、潰瘍性大腸炎の診断 補足の頁を参考に。