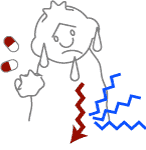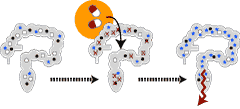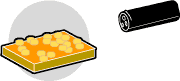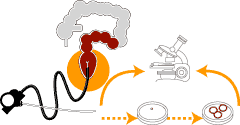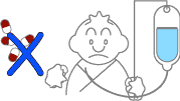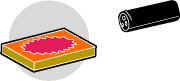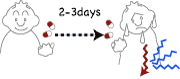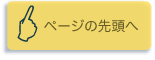大腸炎11 薬剤性腸炎
薬剤でひきおこされる腸炎で、その多くは抗生物質が原因です。偽膜性大腸炎と抗生物質起因性急性出血性大腸炎が代表です(図1![]() )。
)。
抗生物質以外では、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤でもおきます。非ステロイド性消炎剤では胃潰瘍がよくおきますが、稀に大腸炎をおこします。
偽膜性大腸炎
抗生物質をある期間にわたり投与すると、その薬に感受性のある細菌はぐっと数が減ります。競争相手がへるために、逆にその抗生物質に耐性をもつClostridium difficleは腸内で異常に増殖します(菌交代現象 図2![]() )。
)。
この菌が産生する毒素のため、内視鏡で見ると黄白色の小隆起(粘膜壊死物質など)が散在します。重症例ではこの小隆起が融合し、さまざまな形を取ります(図3![]() )。
)。
症状
腹痛、腹満にともない水様下痢がおこります。発熱もみられますが、もともと抗生物質を投与するのは感染症が基礎にあったからなので、発見が遅れがちです。
診断
抗生物質服用している人が水様下痢をきたしたときに、大腸内視鏡をおこないます。ほとんどの例で直腸がおかされ、重症例(治療が遅れた例)では全大腸に病変がおよびます。
内視鏡で特徴のある偽膜が確認できれば診断がつきます(図3![]() )。菌検査でのClostridium difficle同定により確定診断となります(図4
)。菌検査でのClostridium difficle同定により確定診断となります(図4![]() )。
)。
治療
まずは原因となる抗生物質を中止し、対症的に点滴で脱水を改善します(図5![]() )。抗生物質をあらたに加えると、さらに菌交代が進み治療に難渋します。基礎疾患が重篤でなければ、保存療法で徐々に改善します。重症例では、VCMを経口投与します。
)。抗生物質をあらたに加えると、さらに菌交代が進み治療に難渋します。基礎疾患が重篤でなければ、保存療法で徐々に改善します。重症例では、VCMを経口投与します。
抗生物質起因性急性出血性大腸炎
症状
抗生物質(ペニシリン系、セフェム系で多い)の服用後に血性の下痢、腹痛で急激に発症します。アレルギー説や菌交代説などありますが、正確な原因ははっきりしません。
診断
抗生物質服用歴のある血性下痢をともなう患者で、大腸内視鏡で深部大腸に全周性の発赤、浮腫、びらんが認められたときに本症を疑います(図6![]() )。
)。
偽膜性大腸炎と違い、抗生物質服用後2,3日と早い段階でおきやすく、また横行結腸など深部大腸がおかされやすい傾向があります(図7![]() )。
)。
治療
ほとんどの例が抗生物質の中止と輸液などの対症療法で改善します。