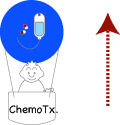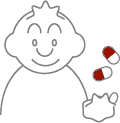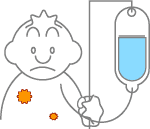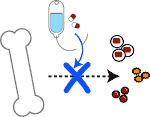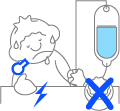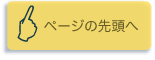大腸癌9 化学療法(1)
手術が大腸癌治療の中心であることは変わりなく、化学療法はあくまで補完的な治療です。例えば血液の癌などとくらべると根治はのぞめず、それだけで病気を治すのは困難です。
大腸癌は従来、化学療法が効きにくい癌の代表でした。しかしその成績も、近年になり飛躍的によくなっています。新しい薬の開発と共に、複数の抗ガン剤を併用する方法が進歩したからです(図1![]() )。
)。
対象
化学療法には癌の縮小、延命をはかる単独化学療法と、手術の後に再発をふせぐための補助化学療法があります。放射線療法とあわせておこなう化学放射線療法については、放射線療法の項を参照してください。
補助化学療法
進行癌で再発をおさえるためにおこなう化学療法で、ふつうは飲み薬でおこないます(図2![]() )。明らかな早期癌で再発の可能性が非常に少ないときは原則としておこないません。
)。明らかな早期癌で再発の可能性が非常に少ないときは原則としておこないません。
単独化学療法
手術後に明らかに癌が残っているとき、術後に癌が再発し手術でとりのぞけないとき、遠隔転移などにより手術ができないときが対象になります。補助化学療法と違い、癌を小さくするためには薬の種類も量も多くなり、副作用もおきやすくなります(図3![]() )。
)。
副作用
補助化学療法では稀に消化器症状がでるだけで、ほとんど副作用はありません。むしろ、副作用がでるようならば、補助化学療法は有害ですので中止します。
単独化学療法は個人差はありますが、副作用は出ます。大腸癌化学療法でおきやすい副作用を以下に記します。
骨髄抑制
抗癌剤は、活発に増殖する細胞の増殖をおさえます。骨髄にも有害にはたらき、血球が減少することも多いのです(図4![]() )。具体的には
)。具体的には
- 白血球 感染症に注意する必要があります
- 血小板 出血したときに血が止まりにくくなります
- 赤血球 貧血になります
骨髄抑制がおこったときには、薬を減量したり、投与法を変更したりします。ただし、その化学療法がたいへん有効で継続することで効果が期待できるときは、顆粒球コロニー刺激因子(Granulocyte Stimulating Factor=GCSF)の使用や血球輸血も行います。
消化器症状
吐き気、下痢が主です。また、食欲不振や便秘をきたすこともよくあります(図5![]() )。
)。
吐き気は薬剤の血中濃度が急速に上がるときに嘔吐中枢が刺激されて、特に静脈投与されたときに急激におこります。制吐剤が進歩し、点滴でもちいることで以前とくらべて、随分と楽になりました。
下痢は抗癌剤を使い始めてしばらくしてからおきます。大腸粘膜も骨髄と同じで、細胞分裂がさかんなところなので、抗癌剤の副作用がおきやすいところなのです。あまり下痢がひどいときには、抗癌剤を減量したり、中断することもあります。
その他の副作用
脱毛や、手足症候群(四肢末端のヒリヒリ、チクチクした知覚過敏や色素沈着など)などが知られています。抗癌剤の種類により、腎障害など生じることもあり、とくに第一回目の治療には厳重な管理が必要です。