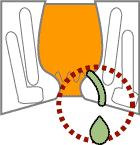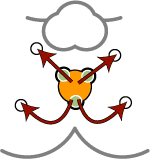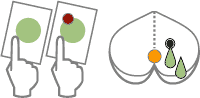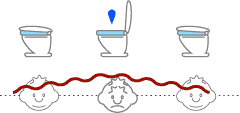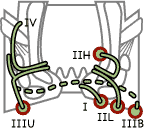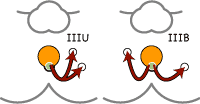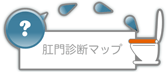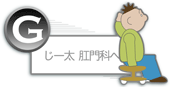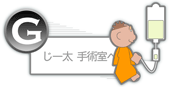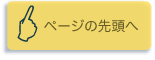痔瘻2 痔瘻の診断と分類
痔瘻の診断
原因
痔瘻(じろう)とは肛門周囲に膿がでる穴があいている病気で、俗に「あなじ」とよばれています(図1![]() )。男性に多い病気で、とくに乳児痔瘻はほとんど男子だけです(図2
)。男性に多い病気で、とくに乳児痔瘻はほとんど男子だけです(図2![]() )。
)。
多くは肛門周囲膿瘍で手術などで膿がでたあと、その口がふさがらず膿が出続けることがはじまりです。それ以外では、裂肛(れっこう=いわゆる切れ痔)は肛門管にできる切り傷で、ときにこの部位が感染し痔瘻になります。また、炎症性腸疾患のクローン病でもよく痔瘻を伴います。
特徴
痔瘻は肛門管内に入り口(原発口)を、皮膚側に出口(2次口)をもつトンネルです。トンネルが完成すると、たえず細菌が肛門側からはいってくるので炎症が持続し、治らないわけです。
トンネルの入り口と出口の関係にはGoodsallの法則(図3![]() 2次口が前方なら原発口は直線的に前方に、2次口が後方なら原発口は曲線的に後方正中にあることが多い)が知られています。ただし、複数の2次口があるような複雑痔瘻は簡単ではありませんが。
2次口が前方なら原発口は直線的に前方に、2次口が後方なら原発口は曲線的に後方正中にあることが多い)が知られています。ただし、複数の2次口があるような複雑痔瘻は簡単ではありませんが。
肛門疾患は良性で手術なしでも治ることも多いですが、痔瘻は手術なしで治ることはありません。手術を早期にしないと難治性の複雑痔瘻となります。
症状
痔瘻になる前には、肛門周囲膿瘍の時期があります。「一月ほど前におしりがひどく腫れて熱が出た。そのあと、痛みが強くなって破れ、膿がたくさん出て楽になったが、いつまでも膿がとまらないので心配になって」というのが典型例(図4![]() ,図5
,図5![]() )。
)。
痔瘻はいったんできてしまえば、ふだんはあまり痛みや熱もなく、出血をともなうことも少なく、ただ下着にウミがつくだけです。ただし、ウミの出る口がいったんふさがると、痛みや熱がでるときもあります。
痔瘻の分類
痔瘻はトンネルの走り方により、大きく4つに分類します(図6![]() )。
)。
- 皮下または粘膜下: I型
- 筋間: II型
- 坐骨直腸窩(ざこつちょくちょうか): III型
- 骨盤直腸窩(こつばんちょくちょうか): IV型
I型の皮下、粘膜下型は一番浅いところを走り、肛門陰窩の感染でなく裂肛や肛門手術などが原因です。
II型は内外の肛門括約筋の間をトンネルが走り、痔瘻の80%をしめます。2次口が歯上線より下へのびる低位(L)と高位(H)に分かれます。
III型は後方に原発口がありトンネルが肛門周囲の後方部分の脂肪組織内深くを走るもので片側(U)と両側(B)に分かれます。たびたび複雑化し2次口を2つ以上有します(図7![]() )。
)。
IV型は稀ながら、さらに上へ伸びたトンネルが肛門挙筋の上まで伸びているものをさします。